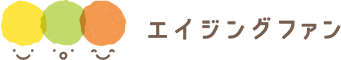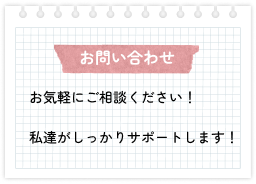「熱が出ているのに、病院の検査で原因が見つからない」、誰しもそんな経験をしたことがあるかもしれません。このような場合、心因性発熱と呼ばれる現象を知っておくと良いでしょう。心因性発熱とは、ストレスが原因で体温が上がってしまう現象のことです。最近、これが発達障害を持つ方々にしばしば見られることがわかってきました。今回は、この心因性発熱と発達障害の関連について、高校生でも理解しやすく解説します。
心因性発熱とは何か

心因性発熱は、心理的なストレスや不安によって引き起こされる発熱のことを指します。よくある症状としては、37~38度台の微熱が長期間続きますが、検査をしてもウイルスや炎症のような身体的原因が見つかりません。その特徴としては次のようなものがあります:
- 長期間原因不明の微熱が続く
- ストレスが強いときに悪化する
- 解熱剤が効きにくい
- 睡眠やリラックスで一時的に熱が下がる
発達障害のある人が心因性発熱を経験しやすい理由
発達障害(例えばASDやADHD)のある人々は、感覚が過敏であったり、社会的なストレスに対する耐性が低いことがあります。ですから、日常生活の中で感じるストレスが非常に強く、知らず識らずのうちに心因性の症状として身体に現れることがあります。特に以下のような場面で心因性発熱が見られることがあります。
- 学校や職場などでの環境の変化に適応できないとき
- 人間関係のトラブルが続いているとき
- 周囲の期待に応えようと無理をしているとき
- 「自分は他の人と同じようにできない」と感じるプレッシャーを抱えているとき
「普通に振る舞わなければ」という自己否定感などがストレスとなり、身体に影響を及ぼすことがあるのです。
心の声に耳を傾けることの重要性

心因性発熱は決して「仮病」ではありません。体温が実際に上がっており、本人にとっては明確な体調不良です。それは、心が助けを求めているサインとも言えます。
発達障害を持つ方に対しては、次のようなサポートが効果的です:
- 本人の感じている「つらさ」に寄り添う
- 静かな空間や予定の見通しを立てやすくするなど環境を整える
- 医療機関と連携し、心身の両面からケアを行う
何より、「どんなことでつらいのか」「どんなサポートが必要なのか」を本人と共に考えることが大切です。
まとめ
発達障害を持つ方々にとって、日々のストレスは目に見えにくいものですが、心因性発熱という身体症状として現れることがあります。体の不調は、心の悲鳴である可能性があります。「原因不明の微熱が続いている」「環境の変化で体調が悪くなる」、そんなときは、心と体の両面から支援することが安心につながります。小さなサインを見逃さずに、共に歩む関係を築いていきましょう。